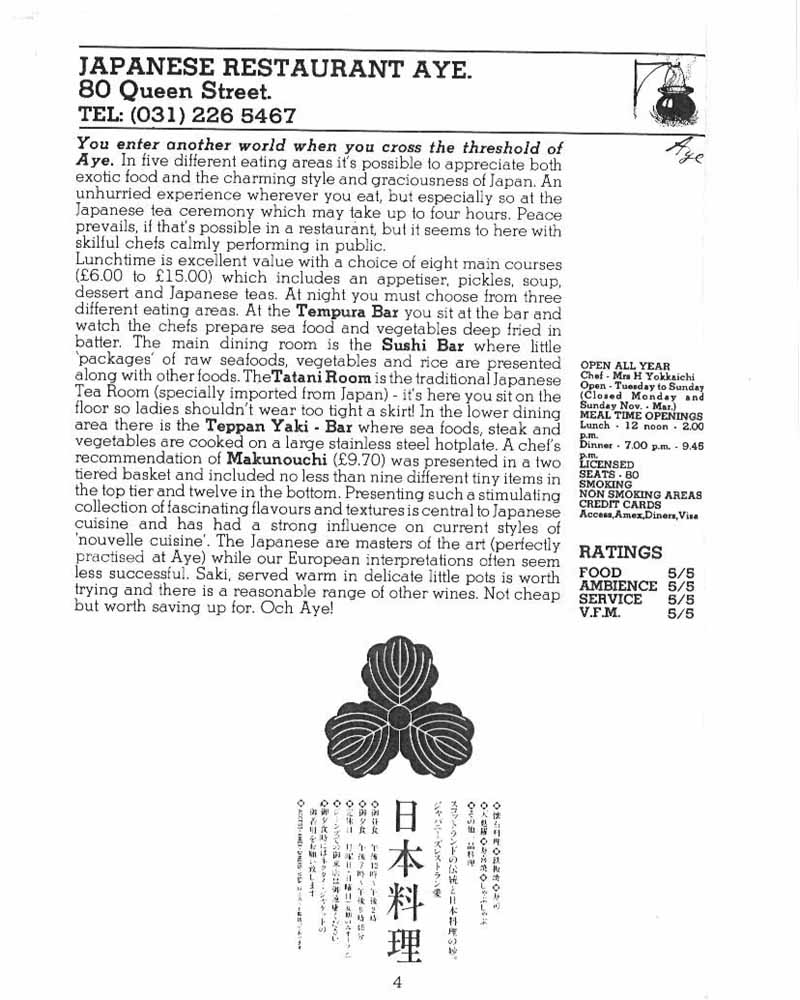���X�R�b�g�����h������ ������ 2012�N��
| �y��58��z 2012�N 11��25���i�j 18:00�` �Q����15�� |
|---|
|
���\�ҁF���� �ҘY����
�e�[�}�F�u���r���E�X�p�[�N�ɂ��āv ���r���E�X�p�[�N�̓X�R�b�g�����h�o�g�̒����ȏ�����ƃ~�����G���E�X�p�[�N�̑��q�ł��B19�˂Ō��������~�����G���́A���������Ă����v�A�V�h�j�[�E�X�p�[�N�̕��C�n���[�f�V�A�i���݂̃W���o�u�G�j�ŁA�����̗��N1937�N�Ƀ��r���݂܂����B �v�����_�a�ŁA�\�͂�U�邤�̂ɑς����˂āA��̃~�����G���̓��r����6�˂̎��ɕv�Ƒ��q���c���ĉp���ɋA�����Ă��܂��A���̌�͍�Ƃ̐l������ނ��ƂɂȂ�܂��B��e�͐l�C��ƂƂȂ�̂ł����A�X�R�b�g�����h�ɂ͋A�炸�A�����h���A�j���[���[�N�A���[�}�Ɠ]�X�Ƃ��A�Ō�ɂ̓C�^���A�A�g�X�J�[�i�n���Ɉ������݁A�ӋC��������������ƃy�l���y�E�W���[�f�B���Ƌ��������𑗂�A�ӗ~�I�ȍ�Ɗ����𑱂��܂��B ��Ɏ̂Ă�ꂽ���r���͕�e���������Q�N��ɃX�R�b�g�����h�ɋA��A�c����Ɉ�Ă��Đ��l���܂��B��������e�Ƃ̊m���͌���I�ŁA�ނ����_���l�̌ւ�����������悤�Ƃ���̂ɁA��e���J�g���b�N���ɉ��@�������ƂɂЂǂ��������܂��B�ނ�40��ɂȂ��Ĕ��p��w�ɓ����āA��Ƃ��߂����A�]���̗ǂ�������i���e�Ɍ��悵���̂ɁA�ޏ��͂�����U�X�ɍ��]����̂ł��B�ޏ����S���Ȃ�O��20�N���炢�́A���݂��ɑS�����M�s�ʂ̏�Ԃ������ƌ����܂��B�ޏ���2006�N�Ƀg�X�J�[�i�ŖS���Ȃ�܂����A����2�N�O�Ɉ⌾�����ٔ����ɒ�o���A�C�^���A�ɂ���ޏ��̑S���Y���҂̃y�l���y�E�W���[�f�B���ɑ���ƌ��߂��̂ɁA���r���̂��Ƃ͈ꌾ���G��Ă��Ȃ������Ƃ̂��Ƃł��B�������C�^���A�̖@���ł́A�̐l�̈�Y�̔����́A���q�A�܂��͖��������ł���̂ŁA���̎葱�����Ƃ邩�ǂ����ƁA�}�X�R�~����q�˂�ꂽ�Ƃ��A���r���͌��݂̐����Ŗ������Ă��邩��A��̍��Y�𑊑��������͂Ȃ��Ɠ������Ƃ̂��Ƃł��B �ނ͉�X�̒m�l�A�G�f�B���o���ݏZ�̐���K�O����̔��p���D�O���[�v�̈���ł�����̂ŁA���삳����b�����낢�땷���܂����B�l���݈ȏ�ɗD�ꂽ�˔\�⎑�����������e�q���m�̊W�͓�����̂��Ǝv���܂����B |
| �y��57��z 2012�N 9��18���i�j 18:00�` �Q����7�� | |
|---|---|
|
���\�ҁF�ꌴ �g�炳��
�e�[�}�F�u�W���K�C���j�݂̈��v
�W���K�C���j�݂̖��Őe���܂�Ă����c���g�i1856�`1951�j�͓y���˂̉������m�̉Ƃɐ��܂�܂������A���̋����͍�{���n����푾�Y�Ɠ����ł����B�ނ̕�����Y�͊��푾�Y�̕Иr�ƂȂ��ĐM���Ă����̂ŁA���g�͊��Ƃ̉����ő��D�A�C�^������邽�߃O���X�S�[��7�N�ԗ��w���Ă����̂ł����A���̊Ԕނ̍s�����̖{���œ����Ă����W�j�[�E�C�[�f�B�i1864�`�H�j�Ɨ����ɂȂ�A�����̖܂ł��܂��B ���������e�̔��œ�l�͌����ł��܂���ł������A���g�͊C�^�A�_�ƂȂǂ̕���ł��̌���{�̊e�n�Ń��[�_�[�V�b�v�����܂��B�ނ͔��قŐ��������̂́A�A�C�������h�n�̃W���K�C���A�A�C���b�V���E�R�u���[�Ƃ��������ď_�炩���i���A�����āA���y�������߂ŁA�ނ��j�݂ɏ������Ă������Ƃ���A����͒j�ݏ��ƌĂ�Ă��Ă͂₳��܂����B �ނ�95�Ƃ���������������1951�N�ɑ��E�����̂ł����A�ނ̔_���������ؑ����v�����_��̑q�ɂ̒��Ŕ��������̂́A����܂ŒN�̖ڂɂ��G��Ȃ�����89�ʂ̃W�j�[�̗����ł����B���̂��Ƃ���Ⴂ���̔ނ̈�������݂ɏo���̂ł����B
|
| �y���56�z 2012�N 7��20���i���j 18:00�` �Q����10�� |
|---|
|
���\�ҁF���c ���q����
�e�[�}�F�u�X�R�b�g�����h�̃t�H�[�N�e�C���Ƃ̏o��v ���c����͋�����ǂ̍������a����Ɠ�������ɒʂ��Ă��Ēm�荇�����������Ƃ���A�u�܂�₩�X�R�b�g�����h�̗��v��2�x�قǗU��ꂽ�̂����������ŁA�X�R�b�g�����h�̖��͂ɖڂ��J������A�X�ɍ����������łȂ��A�ݍF�����A���Y�`�Y����ƒm�荇���ƂȂ������Ƃ���A���Y�搶����X�R�b�g�����h�̖��b�̂������낳��������ꂽ�����ł��B���ꂪ�����[�������̂ŁA���c����͎O�����q�q����Ȃǂƈꏏ�ɁA�����ŃX�R�b�g�����h���b��ǂމ���n�߁A���̎w�������Ƃ��ē��Y�搶�ɋ����𐿂����Ƃɂ����Ƃ̂��Ƃł��B����ȗ����b�̉�̊F�����10�N�ȏ�ɂ킽���ĕ��𑱂��A���Y�搶���S���Ȃ�ꂽ����A����Ɍ����Ŗ��b��ǂݑ����Ă�����Ƃ̂��Ƃł��B |
| �y��55��z 2012�N 5��30���i���j 18:00�` �Q����15�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
���\�ҁF���c ���q����iRSCDS���F���t�j
�e�[�}�F�u�_���X�Ǝ��ƃX�R�b�g�����h�v �E�n�߂� ���̃X�R�e�B�b�V���_���X�Ƃ̏o��͍��Z����ł����B����GHQ�͓�����w�o�ϊw����w�@�����Ɠ��{��s�̊č��������˂�o�ϊw���m�Ƃ��āA�V�J�S��w�̃X�U���i�E���C�J�[���j�𓌋��ɏ����Ă��܂����B�������̌����Ƃ͗����ɁA���C�J�[����͎���Ŗ��T���Ƀt�H�[�N�_���X�̏W�����J�����e�Ɉ�Ă��A���y�ƃ_���X�Ɛl�̘a����D���ȁA���������Ɩ��͓I�ȏ����ł����B�V�J�S�̉ƒ�ł̗l�Ɏ���Ɏ�l���W�߂ăt�H�[�N�_���X���e�[�}�Ƃ���\�V�A���^�C������肽���Ƃ����ޏ��̊�]�ʼn�͎n�܂�܂����B���y�j���̌ߌ�W�܂�̂́A����̉�F�œs���|�����Z�̑̈狳�t�E���G��搶�Ƃ��̐��k�ł��������ƗF�l��l�A�c�����Z�̒j�q���k��l�A����̑�w�@�̒j�q�w�����l�A����̍��ە��̐E�����l�A���킹�ď\���l�Ƃ�����������ł������A�������w���ŁA���E���̑f���炵���_���X���y���ނ��Ƃ��o���F�����ɂȂ�܂����B �����ŏo������̂� Dashing White Sergeant �� Eightsome Reel �ł����B�X�R�b�g�����h�ƌ����Όu�̌��E�A�j�[���[���[�����m��Ȃ��������ɂƂ��Ă��̖����I�ȃ��[���͏Ռ��I�ŁA���y���X�e�b�v����x�ōD���ɂȂ�܂����B 2�N�قnj�ɁA���C�J�[�����YMCA�̑̈�ي����̈�Ƃ��Ă��̃_���X�������n�߁A���͏�����߂܂����B�����Ŋw�l�X����X���{�̃t�H�[�N�_���X�E�����[�h����҂ɂȂ��čs���̂ł����A���̒��ɍ��Z�̑̈狳�t�ł������r�Ԕ��V�����܂����B�t�H�[�N�_���X�̎Љ���̉��l��F�߂��ނ͂₪�ăj���[���[�N��w�̑̈�w���̊w���ƂȂ���5�N�ԁA�X�ɑ̑��̍��X�G�[�f����1�N��6�N�Ԃɐ��E�̃t�H�[�N�_���X���w��ŋA�����܂����B
�E�X�R�b�g�����h�Ǝ��̊ւ��
Royal Scottish Country Dance Society (RSCDS) New York Branch ��Scottish Country Dance (SCD)���w�сASociety �̑n�n�҂ł��� Miss Jean Milligan ���璼�ڎw�����A���̃_���X�ɔM�������r�Ԃ���͋A���㒼���ɋ��ɂ�����n�߂悤�Ǝ���U���܂����B���R�͎����K���M������_���X������ƌ������Ƃł����B��̎��͂Ƃ������A�r�Ԃ���̔M�ӂɉ����ă_���X���Ԃ��W�ߖڍ��旧���ڍ����w�Z�̑̈�قŎn�߂��̂����{���� SCD Club�ARSCDS���ݗ����ꂽ1923�N���璚�x40�N���1963�N�ł����B �����p����g�v�l�͔M�S��SCD �̗x���ŁA��g�ٓ��� St. Andrew Society ����ɂ���R�̗D�ꂽ�_���T�[�������A���ǂ��Ƃ̌𗬂������܂�����ɂȂ�܂����B
1969�N�ɂ͖L�����ŁA���{���̑�X�I�ȃn�C�����h�Q�[���Y���A�r�X�P�b�g�̃}�N���B�e�B�Ў�ÂŊJ�Â���܂����B���X�����Ґ���Argyll and Southerland �A����Bag pipe Band�ƊC������Marin Band ������ʂ���������A�����قő�C�x���g���J��L������ł̊J��ł�������A���̓��킢�͈�ʂ�ł͂���܂���ł����B�������E�`�����s�I���Ƃ��Đl�C�Ⓒ��Billy Forsyth �Ƃ��̒��Ԃ��J��L���� Highland Dance �̉ؗ킳�A�P�C�o�[������n���}�[�A�E�G�C�g�Ƃ������A���ł͂�����݂̎�ڂ��n�߂Ċς�ڂɂ͋��قł����B���̓��f�����X�g���[�^�[�Ƃ��ăX�e�[�W�̏��SCD��x���Ă������́A�����͎����B�ł��̋��Z����������������̂��Ɩ����Ă��܂����B���ꂩ��13�N���o��1982�N�A�����L���X�g����w�����ł�����Dr. Stuart Picken �̋��������͂ŁA���ɑ�1���n�C�����h�Q�[���Y���a�������̂ł��B
���̗��NMiss Milligan �́A�ޏ��̔鑠���q�ł���n���C�ݏZ�� Mrs. Mary Brandon �� Mr. David Brandon �v�Ȃ���{�֔h������܂����B�v�Ȃ͓��{�ɂ�����w���җ{���̕K�v��Ɋ�����A��77�N RSCDS Hawaii Branch �ŋ��t�������i���������{�A�r�Ԃ���Ƌ��Ɏ��͎��Ƃ��ď�����܂����B�������Ƃ��Ă� Miss Milligan �ɂ����Ŏ��͎n�߂Ă��������ł��B����80���ĂȂ����j�Ƃ��Ďw���̐w���ɗ����j�́A�����_�炩���������߂Ȃ���A��X���������Ă�������ꂽ�̂ł��B �uMy daughter, ���Ȃ������邩��A���͓��{�̏������������S�z���Ă��܂���B���ɂ̓X�R�b�g�����h�� Teachers Full Certificate Examination ���t���i�������ɂ�������Ⴂ�B�v���N���j�͖S���Ȃ��A�X�R�b�g�����h�ł̍ĉ�͖��Ə����܂����B�������͎���A����1981�N��St. Andrews �ɉ����� RSCDS�� Summer School �ŋ��t���i�����ɓ��{�l�Ƃ��Ďn�߂ėՂݎ��i���擾���܂����B
1983�N�Ɏ��͍��͖S���v�̓������g���Ƌ���Tokyo Scottish Bluebell Club��ݗ����܂����B
�����RSCDS�ݗ�����60�N�A���{��SCD���x���n�߂Ă���20�N�A�ߖڂ̔N�ɓ���܂��B ����ȗ������܂ŁA����S���Ă���鋳�t�̗{���ɗ͂𒍂��ł��܂����B�L����Ƃɑ�ςȘJ�̗͂v�邱�̎��i�擾�ɔM�ӂ������Ă����l�X�āA��R�̋��t���炿�܂����B���ł͎����������������o����قǂɁB�u���Ȃ����������邩��A���͓��{�̏������������S�z���Ă��܂���v�ƁB �X�R�b�g�����h�Ǝ��̊ւ�荇���́A�_���X�����̑S�Ă̍����ł��B���̂����܂Ő[���ւ������Ɏ��������s�v�c�Ɏv���܂����A���t�̈�l�Ɍ����܂����AMiss Milligan�fs Daughter �����炾�ƁB�ޏ��ɂ����Ăт�����ꂽ������Miss Milligan�fs Boys �ƌĂꂽ�j���́A�N�����̎��f���瓦����Ȃ��A����͔ޏ����g�� her daughter ������ǂ������Ă���Ƃ��B���������b�̂悤�ł����A������^�����Ɗ����Ă��܂��B�����Ă���ł͖����^�����ƁB �����n�C�����h�Q�[���Y�ɗ�N��������� Jim Rae ����Bill Clement���̔鑠���q�A�t���l��Piper��SCD���t�A�������ŔN����Milligan�fs Boy �ł��B�ނ́A����RSCDS���璷�N�̍v���ɑ���h�_�܂������� �hPassing the Torch�h �Ƃ�������SCD��n�삵�����ĉ������܂����BMiss Milligan ���琹�͎��̎�ɁA�����Ď��ɂ͒N���ɁA�����ĉi���ɔR��������ƁB �EScottish Dance.�̓��� SCD�̖��͉͂��Ƃ����Ă����̉��y�ƁA���ꂪ�\�V�A���_���X�ł��邱�Ƃł��BMiss Milligan �́A��ꎟ���E���ň�����l��S�����A��]���������吨�̏����B���݂āA��x�Ɛ킪�N����Ȃ����Ƃ������ Scottish Country Dance Society �� �ݗ����܂����B�X�R�e�B�b�V���_���X�̐��E�ł͒��Ԃ��_���X�t�@�~���[�ƌĂт܂��B��x����Ƃ��ėx�����l�X�͌����Č݂���G�ɂ܂킵�Đ킢�����Ƃ͎v��Ȃ��͂����Ƃ����l�����ł��B ���̊�{�̓\�V�A���_���X�ɂ���܂��B�_���X�̊Ԓ����ɗx��W�l�̒��Ԃ��݂��ɔ��݂����A�����𑗂�A������A�N�ł��������Ȃ��Ɨx���Ă���̂ł���ƈ��A�𑗂�E�E���̒��ɏ����o�����l�̘a�Ɖ��y�̃n�[���j�[�A���ꂪ�\�V�A���_���X�̑�햡�ł��BMiss Milligan��International dance �ƈʒu�Â����ׂɁASCD��Scotland �ɗ��܂炸���E�������鏈�ň��D�҂āA���Ⓦ���E���V�A�ɂ܂ł��x�����o���Ă��܂��BSCD�U�̎�Ƃ��č��ۓI�Ɋy���ސl�����������Ă���̂ł��B�����܂��A����SCD�E���琶�U����邱�Ƃ͖����ł��傤�B �E�X�R�b�g�����h���J �X�R�b�g�����h�ɂ͉i���ɏI���̗��Ȃ� Knot �̃f�U�C���Ɋς�悤�ɗ։��]���̎v�z������܂����A�S���Ȃ�ꂽ���Y�搶�́u�l�͐́X�X�R�b�g�����h�l�������v�ƌ����Ă��܂����B ���鎞���ɁA�l��͗ד��m�������̂ł���A�Ƃ��������ł͂���܂��A�ӂƃ��}���X���Ă��̐��҂��Ă��܂��ƁA�l�͏����Ȓj�̎q�łˁA���ׂɏZ�ނ��k�l���������Ȃ����ƂĂ��������Ă��ꂽ�̂ł���B�ƃj�R�j�R����Ȃ��猾��ꂽ�̂ł��B �_���X���Ԃ̃t�B���X�͑�X�Z���g�A���h�����[�X�̐l�ł����A���������{�l�ł������ƌł��M���Ă����B���w���̎��ɋ�z�ŕ`�����ꂽ���̊G���A�����ɂ�������`�����̂��ǂ�����Ȃ���ɁA���t�ɂ��F�B�ɂ����Đ[�����������Ƃ������������ł��B��l�ɂȂ��ĉp��̋��t�Ƃ��ē��{�ɂ���Ă����ޏ��́A����������X�̑O�œB�t���ɂȂ�܂��B�傫�Ȓg���̐^�ɁA���̎��̂��̒��u�璹�v�������̂ł��B�u��20�N����ёނ�Y��Ă����v���o���h��܂����B �E�I���� JSS�ɐ[�����т��Ă���F������A�����Ƃǂ����ł��� Knot ��繫�����Ă���ɈႢ����܂����B�����Ȃ���A���{�l�Ȃ̂ɁA�ǂ����Ă���قǃX�R�b�g�����h�Ɏ䂩��A�[�����т��Ă��܂����̂��A�䂪�����Ȃ��ł��傤�B |
| �y��54��z 2012�N 3��27���i���j 18:00�` �Q����13�� |
|---|
|
���\�ҁF��� �W�m����
�e�[�}�F�u�T�����C�ɉp����������X�R�b�g�����h�l�v �O�����R�[�̔ߌ���h�����ē��ꂽ�A�[�`�{���g�E�}�N�h�i���h�Ƃ��A�l�C�e�B���E�A�����J�l�̏U���̖����Ƃ���X�R�b�g�����h�l�A���i���h�E�}�N�h�i���h�i1824�`1894�j������̂��b�̎�l���ł��B �����̌��ɂ͓��{�l�̌����������Ă���Ǝv�����݁A���{��K�ꂽ���Ɗ�������i���h�́A20�ŕߌ~�D�ɏ�荞��ŁA�����m�e�n��K��A�Éi���N�i1848�j�ɂ͖k�C���̗��K���t�߂ő�����A�~������܂������A�����̍������x�ɂ���ĊċցE��蒲�ׂ��܂��B �₪�Ē���̏o���Ɉڑ����ꂽ�ނ́A���~�S�Ɋċւ���܂����A�����ɉp��̒ʎ����w�ǂ��Ȃ��������߁A7�����ɂ킽���ĉp��̒ʎ������炵���Ƃ̂��Ƃł��B ���̎��̒�q��14���ŁA���ɏG�˂������X�R�h�V���̓y���[���K�̎��A�p��̒ʎ��Ƃ��đ劈�������ł��B ���̌�Éi2�N�Ƀ��i���h�̓A�����J�̌R�͂Ɉ�������ċA�����A���̌�u�}�N�h�i���h���{��z�L�v�̌��e�������Ă���r���ŁA����27�N�i1894�j�Ɂu�\�C�i���E�}�C�E�f�B�A�E�\�C�i���v�Ɠ��{��ŕʂ�̌��t��ꂫ�Ȃ���A�A�����J�̃I���S���B�ɂ���t�H�[�g�E�R�����B���̎���ŖS���Ȃ����Ƃ̂��Ƃł��B |
| �y��53��z 2012�N 1��19���i�j 18:00�` �Q����20�� | |||
|---|---|---|---|
|
���\�ҁF���� ���N����
�e�[�}�F�u���� ������Edinburgh�v JSS�����E�������N����̑�ϑf���炵���X�s�[�`������܂����B �C�O�Ŏ��Ƃ�����Ƃ͂����������ƂȂ̂ł��傤���B�S���e���Љ�����܂��̂ŁA�������肨�ǂ݂��������B �u�����@������Edinburgh�v �{���́@Scotland�ւ̉��Ԃ��̈�тƂ��āu���{�X�R�b�g�����h����v��ݗ����������̖S�����@�����@�����@��Edinburgh�Ƒ肵�Ă��b���������Ē����܂��B�t�قȓ��e�ƂȂ�Ǝv���܂����AScotland���������S�ōŌ�܂ł��t�����������܂��悤�ɂ��肢�v���܂��B ���������́@�m��A���ƊE�ł́u���������[����v�Ɛe���܂�Ă���܂����B�u���������[����v�ƌ�����Old Parr�ł��̂ł܂���Old Parr �ɂ��Ăł��B Old Parr�@�͖����̌��M�@��q������Ď��@���s�̍ہA���y�Y�Ƃ��ĉp�����玝���A�����ƌ����Ă��܂��B����ȗ��A���{���{�̍����̑�����Old Parr�̈����҂ƂȂ�A�g�c�Ό��A�c���p�h���͓��ɗL���ŁA���U�̌�j�h�ɂ�Old Parr���p����ꂽ�̂͋ƊE�ł͗L���Șb�ł��BLondon�̓��{��g�قł�����g���ڋq�p��Old Parr��p���Ă��܂����B ����Old Parr��ʂ���Scotland��m�����킯�ł����A���߂�Scotland��K�₵���̂́A1970�N�i���a45�N�j��9���ł��B�����A���͐_�˂ɂ���܂����A�o����Ђɋ߂Ă���A�C�O�ւ̗A�o���i�̑D�ώ�z��S�����镔���̐ӔC�҂ł����B���̗A�o�S���ӔC�҂�Scotland��K�₵���̂��H
1970�N�͑��ɂĖ���������J�Â��ꂽ�N�ł��B���̓����͂܂��X�R�b�`�E�C�X�L�[�͗A���g�ɂ���ėA���������Ă���A���A���ʂ͖�30���P�[�X�ł����B���̗A���̑唼��Johnnie Walker�ɏW�����Ă���ADeluxe��2�O���[�v��Lorgan, Buchanan Deluxe, Pinch(Dimple)�ł���AOld Parr�͂������ʒu��6,000�P�[�X���x�ł����B���̗l�Ȓ��A�����p�ɂ͓��ʗA���g���ݒ肳��A���̋߂Ă�����Ђ�Old Parr�̓��{�ɉ�����T�u�̔��㗝�X�ł������A�ʏ��4���̂P�T�C�Y�r��1,000�~�ɂĔ̔�����v��𗧂Ă܂����B
�����̔��\���1000�P�[�X�i4��8��{�j�ł������A����͍D���Ō��ʁA�������Ԓ���3,000�P�[�X��̔����܂����B���ꂪ����@Deluxe Scotch Whisky�̃g�b�v�u�����h�ɂȂ� Old Parr�̔��̕z�ƂȂ�܂����B �听���ƂȂ���4���̂P�T�C�Y�̔��Ď҂́@�A���m���ƊE�ł̎��͎҂ł���������Y���ł����A���̐�����������Old Parr�̐V���ȒS���҂Ƃ��ċ}篎w���B�w�����R�͕����_��2���̌�y�ƕ����������炾�����ł��B�������̂��̎w�����Ȃ���Ε���Scotland�̌q����͖���������������܂���B 1970�N9�����@���͑�㖜���̔̔��@�y�ѓ��{�ɂ�����X�R�b�`�E�C�X�L�[�̏������c����ׂ�Edinburgh�s��K�₷�鎖�ɂȂ�܂����B���̖K��͕��ɂƂ��ď��߂Ă̊C�O���s�ł����̂ŁA���������S�Ă̏����@�@�q�̎�z�i�������ׁ̈@���Ȃ͈�Ԍ��̐ȁj�A�A���s�҂̎�z�i�������̕����ŗ����ꂽ���s�҂Ɂj�BLondon�̃q�[�X���[��`�ł̏o�}���̃A�����W�������ĉ����蕃�͑f���炵����y�Ɋ��ӁA�ȍ~�@�������͕��ɂƂ��đ剶�l�ƂȂ�܂��B �A���J���b�W�o�R�ʼnp������@������London�ɂđ̒��𐮂���Ƃ������z���t���ł��B���͗����A���H���Ƀz�e���̐H�����猩���A�n�C�h�p�[�N�ł̌��i,���Ȃ킿�A���l�̐a�m�i�����n�Ɍׂ��ėI�X�ƒ��̎U�����y����ł�����A�����̒��B�����ӂʼna������ł��镽�a�Ȍ��i�ɊC�O���s�ł̍ŏ��̃J���`���[�V���b�N���܂����B����ȗ��A���͒��H�̃p�����ЂƂ|�P�b�g�ɔE���A�H��̎U���ɒ��B�ƒ��ǂ����邱�Ƃ��p�����s�ł̊y���݂̂P�ɂȂ�܂����B ������London�ʼn߂�������A�t���C���O�E�X�R�b�c�}���ɂ�Edinburgh�̃E�G�[�o���[�w��ڎw���܂����B�������́u���߂Ȃ��A�H�ׂ��Ȃ��A����Ȃ��v�Ƃ����C�O���s�ɂ͕s�K�i�Ȑl���ł����B�u���߂Ȃ��v�Ƃ̓X�R�b�`�E�C�X�L�[�ǂ��납�A���R�[���͑S�R�ʖڂŁA��҂Ɂu�����͂��������ނ悤�ɁI�v�Ɗ��߂��A�Q���r�[�����R�b�v�������炢�͈��߂�悤�ɂȂ������x�ł����B�u�H�ׂ��Ȃ��v�Ƃ͗m�H�����ŁA�����ŏ��ʂ����i���H�ׂ�̂��D�݂ł����B�u����Ȃ��v�A�����͉p����ʖڂł����B���̌�͎Ј��S���ɉp���K�{�Ȗڂɉۂ����ɂȂ�܂����B���݂Ɉ��ތ�̓M���V������w��ł��܂����B ���̗l�ȏ��A����Edinburgh�ő劽�}���A���Old Parr�ł̊��t�A�L�����X�g�����ł̍��ؐH����̘A���Ɩ{�l�ɂƂ��Ă͋�ɂ̘A�������������ł��B��c�͖����ɏI���B���̍ۂ̓��e�������]������A���Old Parr�̓��{�ł̔̔���S�ʓI�ɔC����A���㗝�X�ƂȂ�I�[���h�p�[������Ђ�1973 �N�i���a48�N�j10���ɐݗ����邱�ƂɂȂ�܂��B 3�d��ł�Edinburgh�؍݂ł������A�i�V���i���p�[�N���̒r�ɕ�����ł����R�̐����A�̂�т葐��H��ł�r�A�����ēc�����i�ɐS���߂Ă�������悤�ł��B���ɕ����т�����Edinburgh��̏s��Ȏp�͕������āu�X�R�b�g�����h�͑��̌̋��v�Ƌ��q������悤�ɂȂ�܂��B Old Parr�̍D���Ȕ̔��ɔ����A���̓X�R�b�g�����h�ւ̉��Ԃ����l���܂��B���{�ɉ����Ă�1985�N�i���a60�N�j�ɓ��{�X�R�b�g�����h�����ݗ����܂����B�ݗ��ړI�͂������̒ʂ�ł��B�������ɁA��葽���̕��X�ɃX�R�b�g�����h��K�₵�Ă��炢�����B�Ƃ̎v������Edinburgh�ɗ��s�㗝�X�@Jascot (Japan Scotland�̗�) Travel�Ђ�ݗ��i1984�N5���ݗ��`2001�N9�����U�j�B�����āA���{�̐H�������Љ��ׂɁAEdinburgh�ɓ��{���X�g����AYE���J�X�i1985�N5���J�X�`1988�N3���X�j�����܂����B ���͂��́@Jascot Travel�̗��グ�@�Ɓ@�����X�g����AYE�̊J�X�E�^�c�Ɍg���܂����B
Old Parr������Ђł͉c�Ɗ����̈�Ƃ��Ď���W�҂̕��X���X�R�b�g�����h�ւ����҂��Ă��܂����B�@���s��Old Parr�c�A�[�Ə̂��Ă��܂����B����19�̎��i1974�N�j�Ɍ����҂̕�[�Ƃ��ċ}篖���킩�炸�A���̗��s�ɎQ������K�^�Ɍb�܂�܂����B���̗��s�����ɂƂ��Ă̍ŏ��̊C�O���s�Ł@�X�R�b�g�����h�ւ̑����ł����B���̌�A��x���s�ɂăX�R�b�g�����h��K��A��w���ƂƋ���1977�N����1�N��Old�@Parr������Ђ̊C�O���C����3�l�ڂƂ���Ebinburgh�ɑ؍݂��܂����B
Old Parr�c�A�[�̃A�����W��London�Ɏ��������\����~�L�g���x�����̗��s�㗝�X�ɂ��肢���Ă��܂������AScotland�Ɋւ��Ă͎����B�̕������ʂ������Ȃ��Ă������߁ALondon�̗��s�㗝�X�̃A�����W�ɖ������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂����B����Ȃ�Ύ����B�ŃA�����W���悤��Jascot Travel�̐ݗ��Ƌ��ɁA�O��ł���Edinburgh�ł̏��a�H���X�g�����������B�ŊJ�X���悤�ƕ��͍l���A�������̒S���ɂȂ��Ă��܂��܂����B Jascot Travel��Edinburgh�ɒ����؍ݒ��̓��{�l��ӔC�҂Ƃ��āA���n�̗��s�㗝�X�o���҂��̗p���A�X���[�Y�ɐݗ��o���܂����B1984�N����FAX�̎�z������̂ɁAFAX���̂𗝉����Ă��炤�̂Ɉ��J�������Ƃ��o���Ă��܂��B������v���Ώ��b�ł����A�u�ǂ����āA�d�b������g���ĕ�����]���o����̂��H�v�ƂȂ��Ȃ��������Ă��炦�܂���ł����B�����͊C�O�Ƃ̃r�W�l�X��̌�M�͂܂��e���b�N�X����͂ł����B �܂��o���ł�5�y���X�̌덷�ɑ��āu�⍇���ׂ̈̓d�b��̕���5�y���X�ȏ�ɂȂ邩��C�ɂ��Ȃ��ėǂ��I�v�Ɖ�v�������̐ӔC�҂��猾��ꂽ���ɂ́u���{�ł�1�~�̌덷��100���~�̌덷�̒���v�Ƌ�����Ă��܂����̂ŁA�u���Ɠ��{�ɕ������̂��H�v�ƔY�݂܂����B���Ƃ����{�T�C�h�ɂ͏��K���̈Ⴂ�Ɨ������Ă��炢�܂������B �t�Ɍ��n�̐l�ɗ������Ă��炤�̂���������A�����W������܂����B���{����̖^�L���O���[�v�В��̂��������s���ɖ����Ȃ����ׁALondon����͂��u�В����w�����{�������v���В�����s�̑؍݂���St.Andrews��Hotel�֓͂���Ƃ����A�����W�ł����B�u�����v������͂���A�����W�ł��B��}�ւȂ�Ă���܂���ł����̂ŁA�^�N�V�[�̉^�]��Ɂu���{�������v�������z�e���܂œ͂��Ă��炢�܂������A�u�^�]�肩��͓��{�l�̓N���C�W�[�H�v�ƃp�u�ł̃W���[�N�Ɏg��ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���{�����Scotch Whisky�A���W�҂̒ʖ�˗��ɍۂ��Ă͎����ʖ�Ƃ��ĒS�����A���Ђ̋ɔ�������Ƃ�����܂����B
�܂��S���t��̃A�����W�˗��Ƌ��ɁA�v���C���[����l�̏ꍇ�ɂ͎��������v���C���������Ƃ�����A�A����@���̕��Ƃ͎d���̊W���o���A�𗧂������Ƃ�����܂����B�n�������o�[�̓������K�v�ȃS���t��̃A�����W�̏ꍇ�́A�m�������͒m�����̒m�����Ƀ����o�[�����Ȃ�����q�ˁA�v���C���A�����W�������Ƃ����x������܂����B �X�R�b�g�����h�ł̓S���t���ȒP�ɏo����̂ő����Ƀv���C���y���݂܂����B7�����͎������̎d�����I���ߌ�6������ł�1�����h�o���܂������A�~�͓������R�[�X�̒��ł����E���h���{�[�����]����A�v�������ʂƂ���ɒ��n����̂��m�F���Ȃ���ł��v���[���A�]��Ђǂ����ɂ͓r���Ŏ~�߂���B�Ƃ�����ł����B���{�̃S���t�R�[�X�ł̓n�[�t�X�z�[���ň�x�N���u�n�E�X�ɖ߂�̂����ʂł����ASt. Andrews�ł́@OUT��9�z�[���͍s�����ςȂ��AIN��9�z�[���Ŗ߂��Ă���̂�OUT�EIN�̖{���̈Ӗ��������o���܂����B �n���̕������̐��E�������S���t�N���u�̃����o�[�Ɍ}��������܂������A�����o�[�ɂƂ��ăS���t�N���u�͐������Ќ���Ƃ��ẴN���u�ł����B�����o�[�͂قƂ�ǖ��T���A���܂������ԂɃv���C������̂ŗ\���Œm�������m�K���ɃX�^�[�g���čs���܂��B �������郁���o�[�����Ȃ����ɂ́u������HJohn�͕a�C���ȁH�v�u������A�o�J���X��Spain����B�v�Ƃ�����ł����B�L���f�B�[�͒ʏ�t�����Ɏ����ŃN���u��S�����A������Ԃɏ悹�Ĉ������邩�A�ƑS�ăZ���t�ł����B�����o�[�ł���̓Q�X�g�v���C���[�����ҏo����͓̂��{�ƕς��܂��A���̏��������N���u�ł́A�Q�X�g�̃v���C��͉���1�|���h�ł����B���̃��[�g�ł�����125�~�ł��B���������o�[�ɂȂ�O�ɉ��x�������҂����k���Ă����̂ł����A���̋��z��m�������ɂ́A�ςɈ��g�����̂��o���Ă��܂��B18�z�[���S������炸�ɁA�u���̃z�[�����Ƃɋ߂�����v�Ɠr���ŋA��l�����܂����B ���������o�[�Ɍ}����ꂽ�ŏ��̃v���[�I�����ɂ̓N���u�n�E�X�ɂ��������o�[����u���}��1�t���B���̚��肾�B�v�ƃE�C�X�L�[���P�t���y���ɂȂ�A���̌��20���̃����o�[����u���x�͉��̚��肾�B�v�Ǝ��X�ɓ��l�̊��}���A�f��͎̂��炾�Ǝv���t���d�˂܂����B���ʁA���Ƃ��A��͏o���܂������A�ǂ̃��[�g���^�]���ċA�����̂��o���Ă��Ȃ���ԂŌ�ʗʂ̏��Ȃ������Ŗ{���ɗǂ������ł��B���̓����A�����^�]�͌������Ȃ������̂Ŏ��̂����N�����Ȃ���Α��v�Ƃ̊��o�ł����B ���̓����@�p���͕s���ł��������{�͌i�C���ǂ��A���]�[�g�z�e���t���̃S���t��͓��{�̊�Ƃ������������Ă��܂����B���̓���1�A�^�[���x���[�ł̎v���o�̎ʐ^�����Q���܂����B���̉E�ׂ����[�E�g���r�m�A���[�@���̉E�ׂ��T���f�B�[�E���C���ł��B ���ɁA���X�g����AYE�Ɋւ��Ăł����A������͖{���ɑ�ςł����B1984�N��4���AJascot Travel�̊J�݂Ƌ��ɁA���X�g�����̕����T���̂���`�������Ă��܂����B�����T���͎����B�̑��ŒT����邱�Ƃɂ��܂����B �����̏����́A�u���{�l���s�҂ɂ��֗��ȂƂ���B�v�ł����̂ŁAPrincess Street���炳�قlj����Ȃ�New Town�̈�p�ɂĒT�����܂����B�i�C�����������͂��Ȃ肠��܂������A�����̒��ɂ͗ǂ��ꏊ���Ȃ��̂ŁA�ڐ���t���������ڌ��ŏ��L�҂�����݂��悤�ƌv�悵�܂����B�������̕��������Z��Ђ܂��͔N���@�\�̏��L�ŁALondon�̖{�Ђɉ��x���K��A�v�揑���̎����Ƌ��ɐ������J��Ԃ��܂������A�u���H�X�ɒ��݂���Ɓ@���̕����̉��l��������v�Ƃ̗��R�łǂ����Ă����_��͏o���܂���ł����B��2���������ʂɉ߂����낤�Ƃ��Ă��܂����̂ŁA�����T���̕��@��ύX���A�����̃��X�g�����̔����ɐ�ւ��܂����B ���̍ۂɂ͒n���Łu���H�X�ɐ��ʂ��Ă���ٌ�m�v���Љ�Ă��炢�A�X�C�X���X�g�����̔����ɐ������܂����B�������i���̍ۂɁ@Goodwill�@�Ƃ̍��ڂ�����A�ŏ��͉��̂��Ƃ������o���Ȃ������̂��o���Ă��܂��B�����u�̂���v�ƕ�����܂������A���̊������傫���̂ɂ͋�������܂������A�I�[�i�[�ւ̑��Q�⏞���������킯�ł��B���X�g�����̏ꏊ�� 80 Queen Street�B Princess Street�����, George Street�������2�{�ځBWest End�̊p�n�ƍō��̗��n�����ł����B ���̌�͋}�s�b�`�ŊJ�X�����Ă̏����ɒǂ��܂����B���̍�����A���X�g�����̐ӔC�҂͓����\�肵�Ă������ł͂Ȃ��A�������X�g�����̊J�X�E�^�c�̐ӔC�҂ƂȂ��Ă��܂��܂����B��������28�ʼn���������Ȃ���Ԃł̈��H�X�̊J�X�A������C�O�ł̊J�X�ł����̂őS�Ă̕���ł��ꂼ��̐��E�̕��X�ɂ����b�ɂȂ菀���͐i�߂��܂����B�擾����������1�K�ƒn��������܂����̂ŁA1�K�ɂ͎��i�J�E���^�[�F�V�Ղ�J�E���^�[�A�a���F��ʐȂƐ~�[��z�u�����āA�n��1�K�͓S�J�E���^�[�ƈ�ʐȁA�ۊnjɂ�z�u���邱�ƂɂȂ�܂����B�����̎傾�����Ƃ���ł́A���X�g�����̓����H���A�]�ƈ��̌ٗp�A�e��K�v�Ƌ��̎擾�A�]�ƈ��p�Б�̊m�ۂ����ē��{�l�X�^�b�t�̘J�����̎擾���ł��B �J�X���郌�X�g������ʂ��āu���{�̐H������Scotland�ɓ`����B�v���Ƃ��ړI�ł����̂ŁA�P�K�����͂��̓���London�ɂ���ǂ̓��{���X�g�����������a���Ɏd�グ��ׂɂƑS�Ă̓����ނ���{������H���͍s���܂����B�H���̌��ς���Ɋւ��āA���{�ł�����H���Ǝ҂Ǝ{��̊ԂŒ��ڂ��̊z���m�F�������܂����AScotland�ł́A�H���̌��ς��肪�Ó��ł��邩�ǂ�������������@�T�[�x�B���[�ƌ����E��̑��݂����Ԃɓ��邱�Ƃ�m�����̂����̎��ł��B��Ƃ͓��{�l��H�ƃX�R�b�g�����h�l�̋�����Ƃł������A�u�̂�����v�������ňقȂ邱�Ƃɂ��݂��̐E�l�������ɏ��Ă����̂��v���o���܂��B���{�̋��͈����܂����A�X�R�b�g�����h�͉����܂��B �]�ƈ��͌��n�̗p�̓L���b�V���[�̏����ƃz�[���̒j����2���B���̑���20���͓��{�l�ł����B���{�l�̗p�͓��{�ōs���܂������A�C�O�ł̏A�J�o���̂���҂͂S���B ���{�l�X�^�b�t�p�@�J�����̎擾�����ɑ�ςł����B���̓����@London�ɂ������ۍg���̏��Ђł����A20���̓��{�l�X�^�b�t�ւ̘J�����͎擾���Ă��Ȃ������ƕ����Ă��܂��B�����A�J�������擾�o����̂�20���`30���̌��n�̗p�ɑ��ē��{�l��1���̂݁B���n�̗p�҂������Ă��Ȃ����i�����Җ��͖�E���K�v�s���ł����B���̂悤�ȏ������ŘJ������20������S�Ď擾�o�����̂͒S���ٌ�m�̗͗ʂƂ��������悤������܂���B�J�����؎擾�̘N�͂������ɂ́A���g�̎v������܂����o���܂����B���̎��̊���͍����Y��鎖�͂���܂���B �d����Ɋւ��Ă͋���ނ���ςł����B�X�R�b�g�����h���C���߂��̂ŐV�N�ȋ����ȒP�Ɏ�ɓ��邾�낤�ƍl���Ă��܂����B���A���n�̐V�N�ȋ��͓��{�����ɂ͎g�p�ł��Ȃ���ԂŁA�p��ł�FRESH�ł͑ʖڂ�ALIVE�őQ�������m�ۂ����悤�ł����BScotland�ɂ�Alive�ł͂Ȃ�Fresh�ȋ������Ȃ�Scotland�̋������s�ꂩ��̎d����͒f�O���܂����B ���̓����@Scotland�Ŏ��n���ꂽ���͂܂���London�̎s��ɑ����A���̌�,�ēx�@Scotland�ɑ����Ă��Ă��܂����BLondon�̓��{���X�g�����̑������t�����X�̋Ǝ҂���d����Ă���Ƃ̂��Ƃł����̂ŁA��X���p���̋Ǝ҂���d����鎖�ɂ��܂����B���̒��Ń}�O���̕ۊǂ��܂����ɂȂ�܂����B�}�C�i�X���\�x���}�O���̕ۊǂɂ͓K���Ă���Ƃ����̂ł����A���̗l�ȗ①�E�Ⓚ�ɂ��Ȃ��A���ǁ@��×p�̗Ⓚ�ɂ���z���܂����B ���X�g�����J�X��͋��t�����ځ@�X�ɔ��荞�݂ɗ���悤�ɂȂ�u�Ƃɂ������ł��߂ꂽ���̂������Ă���悤�Ɂv�Ɠ`���Ă��܂����B������A���̒��Ɂu���Ɂv���B���Ȃ菬�Ԃ�ł��������͗ǂ��A�u�g����v�Ɨ����l�����f�B���̎��̋��t�̋����̊�͖Y����܂���B�@Scotland�Łu���Ɂv�͎q���B���T�b�J�[�{�[������ɗV�Ԃ��̂ŁA�u���{�l�͂����H�ׂ�̂��H�v�Ƃ��������ł��B�a�H�̂��i�����̓��e���A���{�����z���ꂽ��ނ̒m�����Ȃ��A�p��ɖ̂Ɉ���ꓬ�����̂����ƂȂ��Ă͉��������v���o�ł��B ���X�g�����́@���@�Ɩ��t�����A�A���t�@�x�b�g�\�L�́@AYE�@�ƌ��肵�܂����B���̊����͓��{�ɉ����Ă�Old Parr�Ђ̊֘A���H�X�ɕt�����Ă��܂����BA�EY�EE�@�̓X�R�b�g�����h�Ɠ��̕\�L�ł���u�͂��v�ƌ����Ӗ������ƒm�茈�肳��܂����B 1985�N5���Ƀ��X�g�������͏����������A2���ɘj�郌�Z�v�V�����̌�A�����ɊJ�X�o���܂����BEdinburgh�ł̏����{���X�g����AYE�̊J�X�͑����̃}�X�R�~�ɏЉ��A���̕]���͏u���ԂɍL����܂����B�c�O�������̂͗����̒l�i���A���n�̈�ʂ̕��X�ɂƂ���ɍ����܂��ʂ����ȉ߂��Ė��������Ȃ��A�Ƃ̍��]����������܂����B ���A���̔N���s��Good Food Guide���Łu���[���b�p��̓��{���X�g�����v�̐܂莆��t�����A�~�b�b�V�F�����E�K�C�h�u�b�N�ł��܂��P�N�������Ȃ��̂ɁA�����őf���炵�����{���X�g�������o�����ƏЉ��Ă����̂��o���Ă��܂��B���݂ɑ��̃��[���b�p���̓��{���X�g�����͂ǂ����f�ڂ���Ă��܂���ł����B �{����Scottish �O�����K�C�h�uA Flavour of Edinburgh�v�̂ݎ茳�Ɏc���Ă��܂����̂Ŏ��Q�v���܂����BAYE��FOOD�AAMBIENCE�ASERVICE,�AValue for Money �S�Ă̕����5�_���_��5�_�̍ō��]�����܂����B���_�̃��X�g�����́A�Љ��Ă��܂�98�̃��X�g�������AAYE�Ƃ���1�XFife�ɂ���܂���PEAT INN��2�����݂̂ł����B ���{��ł̉c�Ǝ��ԁE�x���̏Љ�̌�Ɂu�W�[���Y�ł̂����X�͂��������������B�v�u���[�H���ɂ̓l�N�^�C�E�W���P�b�g�̌䒅�p�����肢�v���܂��B�v�Ɩ��L���Ă��܂����A���̗��R�͌��n�̕��X�͓��ʂȓ��ɂ��߂���������AYE�ɂ����X�������Ă��܂����̂ŁA���{�̕��X�ɂ��@��H���ɍs���悤�ȕ����ł͂Ȃ��@�K���ȕ��������肢���悤�Ƃ̔��f����ł����B���̌��蒼��Ɍ����O�r�[���{��\�ŗL���ȕ��������̃��K�[�ƌy���ł����X����A��������������n���̖ڗ����Ȃ��Ȃɂ��ē����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������ɂ́A���f��������̂ł́H�@�Ƃ̎v���ɂ����܂����B����ȗ��A�h���X�R�[�h�������m�łȂ������X�̕��p�ɁA�W���P�b�g��Dunhill�@�̃l�N�^�C�𐔎�ނ��p�ӂ����đΉ����鎖�ɂ��܂����B���̃T�[�r�X�͂����X�̓��{�̊F�l�ɂ����������ADunhill�ɂ����Œ����܂����B ���X�g����AYE��Jascot Travel��ʂ��đ����̌��n�̕��X�Ƃ��m�荇���ɂȂ邱�Ƃ��o���܂����B�e�z�e���̎x�z�l�AAssistant Manager�AHead Porter���Ƃ͍��ӂɂ����Ē����܂����B�ނ�́A���X�g����AYE�̓��C�o���ł͂Ȃ��A�h���q�̃��X�g�����̑I������������Ɣ��ɍD�ӓI�Ɏ���ĉ������܂����B������N�����҂�v���܂����B�t�ɂ����҂ɂ������邱�Ƃ�����܂����B�O�����C�[�O���X�z�e�������W���[�{�݂����������ۂɂ͂����҂��A���܂�Ĉ�x�����̃N���[�ˌ����o�������Ă��炢�܂����B���n�̃p�u�̃I�[�i�[�Ƃ�Old Parr�X�^�b�t�Ƃ̊W�̂��A�ŁA���ɗF�D�I�ł����B AYE�̃X�^�b�t�������b�ɂȂ����a�@�E�x�@�B�����a�@�͓��{�l�ɂ������������̂ɂ͏�����܂����B��25�ɂȂ閺��Edinburgh��Western General Hospital�ɂďo�Y�ł����B���̍ہA�S���s���̕⋋�ɂƔD�Y�w�ɃM�l�X�E�r�[�����z��ꂽ�̂ɂ͋�������܂����B �x�@��AYE���{�l�X�^�b�t���n���̎�҂ƌ��܂������ہA�܂�����ɂ������ۂɌĂяo���ꂽ������܂����B�����Scotch�@Whisky�����݂Ȃ��犰���ł���Ƃ��ɌĂяo����A���L����ԂŌx�@�ɍs���Ă����e�ɑΉ����Ă��炦�܂����B���̑��A���{�l�̎��̂̍ۂɂ��菕�����K�v���ƁA�Ăяo���ꂽ���Ƃ�����܂����B Edinburgh��`��BA�X�^�b�t�ɂ͖{���ɂ����b�ɂȂ�܂����B���{�ւ̋A���ւ̉ו���Edinburgh��`�ɂă`�F�b�N�C������ۂɁA�K��d�ʃI�[�o�[�ł����Ă��lj������̓T�[�r�X���Ă�����Ă��܂����B������X�g����AYE�ɂ͂����҂��Ă��܂����B���������ł��̂ŁE�E�E�B�@���ې��S����Immigration Officer����̌Ăяo����1�x��2�x�ł͂���܂���B�ł��F����{���ɍD�ӓI�ł����B �@Edinburgh Festival�̊J�Ê��Ԓ��A���X�g����AYE�ɂ͓��{�ł͂��ڂɂ�����Ȃ������̒����l�������X�������܂����B�w���҂̏���玂���͌����㖈�Ӑ��l�̉��t�҂ƂƂ��ɂ����X������A���̓N���b�V�b�N���y����D���ł��̂ŁA�u�撣���Ăėǂ������I�v�Ƃ̋C�����ɂȂ������Ƃ��o���Ă��܂��B�����E���i�E�l�Ƌ��ɏo�O�̒����������Ƃ�����܂����BSt.Andrew�ł̃S���t���ł̍��e��B�����̐V���S���O�r�[�`�[���̉������Z�v�V�����BGlasgow�ł̃C�x���g�ɂĎ��i�E�a�H�R�[�i�[�ɂĘa�H���Љ���̂��ǂ��v���o�ł��B��������E�����̓��{�l�S���t�@�[�ɂ����Œ����܂����B �@�����AScotland�ɐi�o���Ă������{�̊�Ƃ�NEC�A�O�H�d�@�A�M�z�����́A��a�X�|�[�c���炢�ŁA���{�l���100�����őg�D����Ă��܂����B��X�̓��{�l�X�^�b�t�����Ԃɓ���Ē����S���t��ɂ��Q�������Ē����܂����B�{����Edinburgh Festival�̃p���[�h�Ɍ�_�`��S���A�Ԋ}�������I�����ۂ̎ʐ^�����Q�v���܂����B���̃p���[�h�̓��X�g����AYE�����S�ɂȂ��čs���܂��������{�l��̕��X�ɂ����Q�������܂����B
1987�N�H����́A����܂ňȏ�ɓ��{�Ƃ̘A���������܂����B1986�N�͉p���ŁA���Z�E�r�b�O�o�����s��ꂽ�N�ł��B���̉e�����炩�A���̌�@��Ɣ������p�ɂɂȂ�AOld�@Parr�u�����h�����L���Ă��܂���DCL���K�͂ł�DCL����������GUINESS�Ђɔ�������Ă��܂��܂����B���̌��ʁA���{��Old Parr ������Ђɂ��㗝�X�_�����������|�̍��m�����͂��Ƃ����厖�ԂɌ������Ă��܂��܂��B���͌��n�@�X�R�b�g�����h�ٌ̕�m�Ƌ��ɏ������W������A���{�̖{�Ђ���̖₢���킹�A�w���ւ̑Ή��ɖZ�E����܂����B�@����܂ł��@���X�g����AYE�͌��j���݂̂��x�݂ŁA�I�t�B�[�X�͓��j�����x�݂ƁA���͋x�ޓ�������܂���ł����B���̍������9���Ԃ̎����̊W�œ����̒�9���́@Edinburgh�ł͖��12���ł��̂ŁA�[��ɂ��`�`�Ɠ��{����̘A�����͂��܂��B�������Ԃ̋��j����̎w���A�����ň��ŁA��������́u����`�@�T�����ŗǂ����璲�ׂĕ������B�v�Ɨ]�T�������Č����Ă��A���̎��Ԃ�Edinburgh�̌ߑO���B���j���Ȃ̂ʼn��������Όߌォ��͑��肪���܂�Ȃ����Ƃ��\�z����A2�`3���Ԃ������Ƃ����ł����B
��������x�@�����悤�ɂ��I�ƌ����Ă����̓I�ɂ������ł��B ���ǁ@��Ɣ����̗���ɂ͋t�炦��1988�N3���Ɂ@���X�g����AYE�p�����AJascot�@Travel�͌��n�ӔC�҂ɔC���Ď��͓��{�A�����܂����B���̌��Jascot Travel�͑������Ă��܂����̂ŕ��͑��E����1993�N3���܂Ńu���b�N�v�[���ł̃_���X�����y���݂ɉp���K��͑����Ă��܂����B�����@Old Parr��Standard Whisky Claymore Brand��DCL���瑼�Ђ֔��p���ꂽ�W��Scotland�Ƃ̃r�W�l�X�͑����Ă��܂����B���݂͂���Claymore�@�����Ђ̈����u�����h�ƂȂ�A���C�������J�[������ЂƂ��Ă�Scotch Whisky�̎戵�͂���܂���B �ȏ�Łu���@����������Edinburgh�v������,����ɔ����u����Edinburgh�v�̘b���I��点�Ē����܂��B�������@���ɗL��������܂����B |
Copyright 2002 The Japan-Scotland Society All right reserved ©