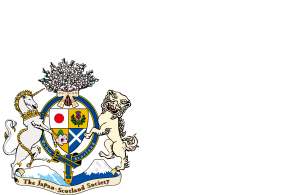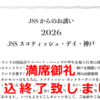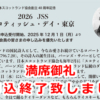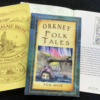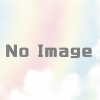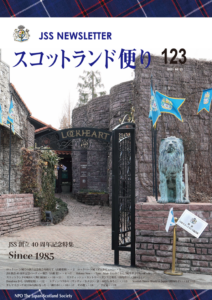JSS高橋&ハワット記念・奨学生 帰国報告会
高橋&ハワット記念奨学金の奨学生、寺岡英晋さん、柴田陽子さん、長田知実さんの、帰国報告会における発表です。
体育教育学部分野での博士課程留学を振り返って
寺岡英晋
2016年度奨学生 ストラスクライド大学大学院
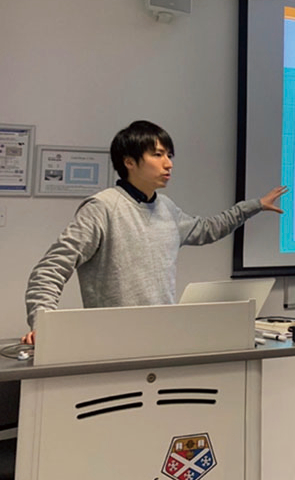
私は「高橋&ハワット記念奨学金」の2016年度奨学生として、2016年から2020年にかけてスコットランドのグラスゴーにあるストラスクライド大学大学院に留学し、スポーツ教育学の分野で博士号(Ph.D.)を取得しました。本稿では、研究の概要や成果に加え、スコットランドでの生活のようす、そして今後の展望についてご報告させていただきます。
私の研究は、スコットランドの中学校における体育の授業が、生徒たちの健康とウェルビーイング、特に心の健康にどのような良い影響を与えられるかを探るものでした。世界的に子どもや若者のメンタルヘルスが深刻な課題となる中、「Pedagogies of Affect(情意の教育)」という理論的枠組みに注目し、教師の授業中のふるまいや関わり方が、生徒の主体性や自己肯定感、肯定的な感情にどのようにつながっているのかを調査しました。この研究では、授業を直接見学したり、生徒と先生にアンケートやインタビューを行ったりする方法(混合研究法)を取り、スコットランド各地の中学校7校でフィールドワークを実施しました。現地の学校では、教師が授業づくりにおいて大きな裁量をもち、生徒一人ひとりに合わせた関わりを大切にしていることが印象的でした。また、学力だけでなく、学びの過程や生徒の人間的な成長も評価の対象とされている点に、日本との違いを強く感じました。これらの気づきは、私の研究をより深めてくれたと同時に、日本の教育にも活かせるヒントがたくさんありました。
留学先としてスコットランドを選んだのは、筑波大学の修士課程在学中に出会ったデービット・カーク(David Kirk)教授の存在が大きなきっかけでした。国際セミナーで同教授の講義を受け、世界的な視野で体育教育を学びたいという思いが芽生えました。さらに、スコットランドの「カリキュラム・フォー・エクセレンス(Curriculum for Excellence)」は、健康とウェルビーイングを教育の大きな柱の一つと位置づけており、私の関心と非常に合致していました。
異文化の中で暮らす、日常生活からの学び
グラスゴーでの生活は、研究活動に加えて、日々の暮らしや人々との関わりの中に数え切れないほどの学びがありました。最初の1年間は郊外のペイズリーという町の学生寮で過ごし、2年目以降はグラスゴー市内中心部のフラットで、他学部の大学院生と共同生活を送りました。フラット探しや手続き、日用品の購入など生活の立ち上げは簡単ではありませんでしたが、地域の人々の親切なサポートに何度も助けられました。困った時に声をかけてくれる隣人や、店員さんとの何気ない会話に、スコットランドのあたたかさを感じました。
異文化に触れる中で、特に印象に残っているのは、日常生活の中に息づく価値観の違いです。雨の多いグラスゴーでは、少しでも晴れると人々がいっせいに公園やテラス席に出て、太陽の光を存分に楽しむ姿が見られます。そのようすには「今を大切にする」心のゆとりが感じられました。また、毎年11月には「リメンブランス・ポピー」を胸に飾る人が多く、戦争の記憶や犠牲者への追悼の意識が社会に深く根づいていることも印象的でした。さらに、パブ文化もスコットランドならではのものです。週末の夜には老若男女が集まり、お酒を片手に語り合い、音楽を楽しむ時間が広がっていました。私も“The Counting House”や“Sloans“といった歴史あるパブを訪れ、地元の方とスポーツ談義を交わすことが日々の楽しみの一つとなっていました。年越しイベント「ホグマネイ(Hogmanay)」では街中が祝祭ムードに包まれ、大晦日から元日にかけて花火や音楽で盛大に新年を迎える体験も忘れられません。
こうした異文化での暮らしや研究活動は、単なる知識の習得にとどまらず、異文化理解力、人間力、自己認識の深化、そして困難を乗り越える力(レジリエンス)といった多面的な力を育んでくれました。現在は日本体育大学で教員として勤務していますが、スコットランドでの学びを日本の体育教育に活かすとともに、学生たちにも国際的な視野を持って学ぶことの楽しさと意義を伝えていきたいと考えています。
最後に、このような貴重な機会を与えてくださった日本スコットランド協会の皆さまをはじめ、現地で支えてくださった先生方や友人、そして家族に深く感謝申し上げます。スコットランドでの4年間は、私の人生におけるかけがえのない財産であり、私のアイデンティティの一部となっています。本当にありがとうございました。
グラスゴーでの生活は、研究活動に加えて、日々の暮らしや人々との関わりの中に数え切れないほどの学びがありました。最初の1年間は郊外のペイズリーという町の学生寮で過ごし、2年目以降はグラスゴー市内中心部のフラットで、他学部の大学院生と共同生活を送りました。フラット探しや手続き、日用品の購入など生活の立ち上げは簡単ではありませんでしたが、地域の人々の親切なサポートに何度も助けられました。困った時に声をかけてくれる隣人や、店員さんとの何気ない会話に、スコットランドのあたたかさを感じました。
異文化に触れる中で、特に印象に残っているのは、日常生活の中に息づく価値観の違いです。雨の多いグラスゴーでは、少しでも晴れると人々がいっせいに公園やテラス席に出て、太陽の光を存分に楽しむ姿が見られます。そのようすには「今を大切にする」心のゆとりが感じられました。また、毎年11月には「リメンブランス・ポピー」を胸に飾る人が多く、戦争の記憶や犠牲者への追悼の意識が社会に深く根づいていることも印象的でした。さらに、パブ文化もスコットランドならではのものです。週末の夜には老若男女が集まり、お酒を片手に語り合い、音楽を楽しむ時間が広がっていました。私も“The Counting House”や“Sloans“といった歴史あるパブを訪れ、地元の方とスポーツ談義を交わすことが日々の楽しみの一つとなっていました。年越しイベント「ホグマネイ(Hogmanay)」では街中が祝祭ムードに包まれ、大晦日から元日にかけて花火や音楽で盛大に新年を迎える体験も忘れられません。
こうした異文化での暮らしや研究活動は、単なる知識の習得にとどまらず、異文化理解力、人間力、自己認識の深化、そして困難を乗り越える力(レジリエンス)といった多面的な力を育んでくれました。現在は日本体育大学で教員として勤務していますが、スコットランドでの学びを日本の体育教育に活かすとともに、学生たちにも国際的な視野を持って学ぶことの楽しさと意義を伝えていきたいと考えています。
最後に、このような貴重な機会を与えてくださった日本スコットランド協会の皆さまをはじめ、現地で支えてくださった先生方や友人、そして家族に深く感謝申し上げます。スコットランドでの4年間は、私の人生におけるかけがえのない財産であり、私のアイデンティティの一部となっています。本当にありがとうございました。
社会人入学で森林資源の活用を研究
柴田陽子
2023年度奨学生 エディンバラ大学ビジネススクール
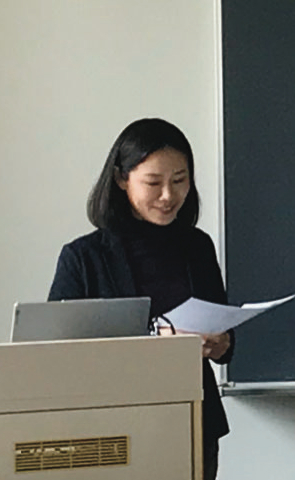
エディンバラ大学にて、気候変動ファイナンス(MSc in Climate Change Finance and Investment)を専攻し、2024年11月に無事、修士課程の修了の認定を受け卒業することができました。このコースでは、気候変動対策に資する金融施策や投資のあり方について理論と実務の両面から学ぶことができ、授業は欧州を中心とした最新の気候政策やカーボンプライシング制度などがテーマとして取り上げられ、知識を深めることができました。
当大学は気候変動などのサステナブル・ファイナンス分野における先駆的な教育機関であり、国際的な排出権取引市場などの金融制度やルール設計に関する知見を深める上で最適な環境でした。実際、このコースのプログラムでは、エネルギー会社や金融機関から来た人が効果的に学べるように設計され、またクラスメンバーも多様になるよう配慮された人員構成になっており、密度の濃い1年間でした。個人的には、山登りが趣味なので、自然豊かなスコットランドの環境も魅力的でしたし、オークニー諸島にも訪問でき理想的な学びの地でした。
備忘として、1年間のコースの学費がEU圏外の学生の場合、2万7,000ポンドとなっており(現在は約3万ポンド)、当時のレートで約500万円という日本では考えられないような金額でしたが、今後の自分への投資と捉えるようにしています。
修士論文では、森林とカーボンクレジット市場(注:企業などが二酸化炭素(CO₂)排出量を取り引きする市場)のとの関係性をテーマとし、日本における森林由来クレジットのポテンシャルについて分析を行いました。複数のシナリオを設定し、その仮定の上でカーボンクレジット発行量を推計し、森林資源の活用の可能性を示せたのではと考えています。
私は日本の大学や大学院では農学部を卒業しており、その際には森林破壊や森林管理について専攻していたので、理系的な知識や社会科学的な分析手法については知識として持ち合わせていましたが、社会人を経験した後で今回のビジネススクールへの留学ができ、これまでの知識にプラスして経済や金融に関する視野が広がり良かったなと思っています。
世界の潮流としてベジタリアンが増えている
当時1ポンドが200円台になる記録的な円安の中で、日々の生活は自炊が主でしたが、日本食が懐かしくなることもありました。アジア系スーパーにあるラーメン5袋のパックが7ポンドほどしており、価格は高いけど食べたい気持ちの方が勝ってしまい、ついつい買ってしまっていました。
イギリスやスコットランド料理を多く食べていたわけではないので、よく「イギリスの料理はおいしくなかったでしょ?」と聞かれますが、エディンバラ滞在中は食に関して不満を感じることはなかったです。ただ、日本に帰国して、何を食べてもすごく美味しく感じるようになったのは不思議です。
私が在籍していたコースでは気候変動問題に真剣に取り組む人が多く、宗教上の理由以外でベジタリアンになっている欧米の人が何人いました。これは、家畜の育成時には野菜の栽培時よりも二酸化炭素を多く排出するということや、動物愛護の観点から肉を食べない選択をしているようです。イギリス以外のヨーロッパに住む私の日本人の友人なども、選択的ベジタリアンが多くなってきているという話をしており、日本ではまだ見られないけれども世界の潮流として、ベジタリアンが確実に広まっていることを感じました。
留学をしたことで、日々の仕事に追われていた生活から少し距離を置くことができ、人生全体を俯瞰して見る機会になりました。また、これまで持っていた環境問題への課題感と解決策としての経済的な仕組みに関して集中して考えることができ、幸せな時間だったなと思っています。
今後のキャリアは、できればカーボンクレジットや森林に関われるような仕事を生涯続けていきたいなと考えています。
日本スコットランド協会やメンバーの皆様、本当にありがとうございました。
国際関係学発祥の地、スコットランドで学ぶ
長田知実
2023年度奨学生 グラスゴー大学大学院

2024年12月にグラスゴー大学大学院(The Masters in International Relations)を修了し、無事に卒業式を迎えることができました。この場をお借りして、これまでご支援いただきました日本スコットランド協会に、心からお礼を申し上げたいと思います。
また、3月の奨学生帰国報告会でも多くの会員の皆様にお越しいただき、誠にありがとうございました。会員の方々と直接交流できたこと、また元駐スウェーデン大使の大塚清一郎さんから私の発表に対して講評を頂戴し、外交官時代の貴重なお話をうかがえたことは、本当に良い経験となりました。このような素晴らしい機会を設けてくださり、あらためて感謝申し上げます。
今回は、私が留学したグラスゴー大学について紹介させていただきます。スコットランドへ留学を検討されている方や、旅行を計画している方の参考になれば幸いです。
グラスゴー大学は1451年に設立され、今年で創立574年を迎えます。世界で4番目に古い大学の一つで(諸説あり)、有名な卒業生としては、経済学の父アダム・スミスや、日本ウイスキーの父とされる竹鶴政孝、電力の単位「ワット(W)」の名前の由来となったジェームズ・ワットなどがいます。メインキャンパスは、ハリーポッターに出てくるホグワーツのようなゴシック建築で、卒業式などの重要な行事が行われます。授業は周辺の現代的な校舎で行われることが多かったです。
グラスゴーの人々は温かく、移民や留学生に対しても非常に寛容で、治安も比較的良かったです。また大学周辺にはアジア系スーパーが複数あり、よく日本食を作りました。
一方で、天候はなかなか厳しく、日照時間が短い上(冬は5時間ほど)ほぼ毎日雨が降ります。また、大学院生専用の寮(Maclay Residences)に1年間住みましたが、シャワー・トイレ付きの個室に、共用のキッチンがある快適な環境であるものの、家賃は月15万円ほどでした。それでも市内では安い方という印象です。
グラスゴーで生活して良かった点は、週末や休暇に退屈することはほとんどなかったことです。美術館や博物館のほかにも、ミュージカルやバレエが頻繁に上演され、私も何度か劇場に足を運びました。さらに、BBCスコットランド交響楽団の演奏会も定期的に開催され、学生であれば千円ほどでチケットが購入できます。こうした文化的な体験を気軽に楽しめる点で、グラスゴーは非常に魅力的な都市でした。
グラスゴー大学の魅力
進学先を決める際、イングランドにあるダラム大学からもオファーが来ていました。ダラム大学も美しいキャンパスを持ち、ハリーポッターのロケ地として使われた建物もあります。ただ、ダラムは地方都市に位置し、自然豊かではあるものの、私にとっては物足りなさを感じるかもしれないと思いました。その点、グラスゴーはスコットランド最大の都市で、都市ならではの刺激と利便性から、留学生活を飽きることなく充実して過ごせると考え、最終的にグラスゴー大学を選びました。
また、私は日本の大学で国際関係学の学士号を取得していたため、国際関係学発祥の地ともいわれるスコットランドで、本場の学問に触れたいという強い思いがありました。グラスゴー大学が提供する国際関係学のコースは比較的高い評価を受けており、私が在籍していた際にはセント・アンドリュース大学に次いで全英2位のランキングでした。また国際関係学のコースではEU研修旅行が含まれ、こうした研修旅行はすべての英国の大学で実施されているわけではなく、とても魅力的に感じました。私も研修旅行に参加し、1週間ブリュッセルに滞在しながらEUの施設を見学し、また観光を楽しむこともできました。
もしスコットランドやグラスゴー大学への留学にご興味があり、ご質問などありましたら、どうぞお気軽に私のメールアドレス(satoplum@icloud.com)までご連絡ください。このレポートが、これからスコットランドやグラスゴー大学への留学を考えている方々の参考になり、少しでも背中を押すきっかけとなれば幸いです。